中島らも 著 (1994年)
1997年に映画化された作品(映画タイトルは「lie lie lie」)
DVDやBlu-ray化されておらず、見る方法はVHSかリバイバル上映ぐらいしかない幻の映画です。
端的にこの作品を説明すると、写植屋である主人公の前に現れた詐欺師とともに本を出版する物語です。
中島らもさんの小説を読むのは初めてですが、非常に魅力的な作品だったのでレビューすることにしました。
あまり文学をレビューする経験はなかったのでつたない文章をお許しください。
印刷技術について
僕は本は読むものの、凸版印刷と凹版印刷の違いも知らなかったのでいい勉強にもなりました。
写植とは
写真植字(しゃしんしょくじ、略称は写植、英: phototypesetting, photocomposition)は、写真植字機を用いて文字などを印画紙やフィルムに印字して、写真製版用の版下などを作ること。また長らくテレビ放送用のテロップ用の版下としても使われた。
多くのサイズの活字が必要な活版印刷に対し、写真植字では1個の文字ネガで足りる。オフセット印刷の普及とともに、写真植字も急速に需要を拡大した。
文字のネガをレンズで拡大または変形して印画紙に焼き付けるので、独特の柔らか味がある事が写真植字のメリットの一つである。DTPが普及した昨今でも、タイトル文字などに限って写真植字を指定して使うケースが見られる。
また、写真植字の歴史は、写研の歴史そのものとも言える。
文字の大きさの単位をQ(または級)、文字の送り量の単位をH(または歯)とする。いずれも0.25mmを1とする。すなわち24Qといえば6mmの大きさの文字を意味する。
(Wikipediaより引用
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%A4%8D%E5%AD%97 )
主人公はそれをコンピュータで行う「電算写植機」を使う写植屋でした。
なお今ではデジタル化が進み、写植屋は減少しているようです。
本はどのように変わっていくのか
「本というものはね……近い将来に失くなるんではないかと思っているのです」
中島 らも. 永遠も半ばを過ぎて (文春文庫) (p.132). 文藝春秋. Kindle 版.
本という形態がなくなるだろうと考えてます。電子メディアにとって代わられるだろう
中島 らも. 永遠も半ばを過ぎて (文春文庫) (p.133). 文藝春秋. Kindle 版.
今、本屋に出まわっている本は、本の体裁をなしておりますが、すでに本ではない
中島 らも. 永遠も半ばを過ぎて (文春文庫) (p.133). 文藝春秋. Kindle 版.
医師協同組合にプレゼンするシーン。本の耐久性について医師協同組合に説明しています。
本は紀元前数世紀の時代の書物が残っているように、何世代にも伝えられるものであるべきだが、数十年しか持たない本に対する批判が書かれています。
また、本書では紙からフロッピーに代わるだろうと書かれていましたが実際はフロッピーがいろいろなものに代わっていきましたね。
しかし、僕はこの本を紙ではなくkindleで読んだので、電子メディアに置き換わるといった点はその通りだと思いました。紙の本の発行部数はこれから少なくなっていくんだろうなと感じます。
詐欺師たちの作品はなぜ魅力的なのか
現実の詐欺は許されない行為ですが、作品に出てくる詐欺師たちはとても魅力的であると思っています。
最近ではNetflixで公開された「地面師たち」が流行りました。自分はまだ見ていないませんが、Youtubeに投稿されているシーンだけでも面白いと感じました。
詐欺師の美学・思考
報酬は関係がない
騙し取る金額の問題ではなくて、プロセスに「味がない」のだ。
中島 らも. 永遠も半ばを過ぎて (文春文庫) (p.44). 文藝春秋. Kindle 版.
今作に出てくる相川が最初に東京でやった詐欺は”お目見得詐欺”。求人広告を出している中小企業の工場に行き雇ってもらう際に、すぐに働きたいから当座の金を前借したいと持ち掛ける。この詐欺に対して、相川は「味がない」と語ります。
しかし、手間がかかり、リスクの大きい ”取り込み詐欺” は儲けはそこまで多いわけではないのにも関わらず興奮する。
この感覚は怪盗にも通じるところがあると思いました。例えば「物は盗んでも人の命は盗まない」や「必ず予告通りに盗む」などです。
悪党であっても、そこに美学を感じればそれが魅力の一つに見えます。
役者とペテン師
「役者とペテン師は、首から下に汗をかくんだ」
中島 らも. 永遠も半ばを過ぎて (文春文庫) (p.148). 文藝春秋. Kindle 版.
医師協同組合にプレゼンした後の詐欺師のセリフ。
写植屋の方は昔演劇の経験があり、プレゼンでは焦っているような素ぶりを全く見せずにその経験を活かし、プレゼンに成功しました。
バレないかというスリル
詐欺師たちが出てくる作品の一番の見どころは詐欺がバレそうになるところです。
作中では終盤に偽書を出版することに成功しましたが、ある人物に偽物ではないかと疑われてテレビで討論することになりました。その人物はとても文学に詳しいため、付け焼き刃の知識しかない主人公たちが果たしてどうするのか、ぜひ読んでみてください。
「孤独」について
孤独というのは、「妄想」だ。孤独という言葉を知ってから人は孤独になったんだ。同じように、幸福という言葉を知って初めて人間は不幸になったのだ。
中島 らも. 永遠も半ばを過ぎて (文春文庫) (p.173). 文藝春秋. Kindle 版.
人は自分の心に名前がないことに耐えられないのだ。そして、孤独や不幸の看板にすがりつく。私はそんなに簡単なのはご免だ。不定型のまま、混沌として、名をつけられずにいたい。この二十年、男と暮らしたこともあったし一人でいたこともあったけれど、私は自分を孤独だと思ったことはない。私の心に名前をつけないでほしい。どうしてもというなら、私には一万語くらいの名前が必要だ。
中島 らも. 永遠も半ばを過ぎて (文春文庫) (p.173). 文藝春秋. Kindle 版.
中盤から登場する出版社に勤める宇井の言葉。自分の心に名前を付けたくないために「孤独」という言葉を嫌います。
しかし、詐欺師たちに出会い、写植屋と恋に落ち、最後には考えが変わります。
この人のせいで、私は孤独の意味を今度こそ知るだろう。でも、私は恐れない。
中島 らも. 永遠も半ばを過ぎて (文春文庫) (p.249). 文藝春秋. Kindle 版.
この考えの変化が文学的でとてもきれいなオチだと思いました。
語りつくせなかったことがまだまだ
ブログ記事にするために要素をできるだけ省いてみましたがまだまだ語りつくせないことが多くあります。ページ数もめちゃくちゃ多いわけでもなく、文体も柔らかいので読みやすい小説なので気になった方はぜひ読んでみてください。
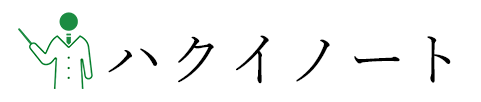

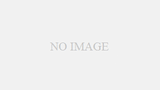

コメント